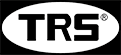拡大する
スピーカーがマルチチャンネル同時入力に対応しているかどうか、パッシブサラウンドスピーカー用の出力インターフェースがあるかどうか、USB入力機能があるかどうかなどを指します。外部サラウンドスピーカーに接続できるサブウーファーの数も、拡張性を測る基準の一つです。一般的なマルチメディアスピーカーのインターフェースは、主にアナログインターフェースとUSBインターフェースです。光ファイバーインターフェースや革新的なデジタルインターフェースなどは、それほど一般的ではありません。
効果音
ハードウェア3D音響効果技術として、SRS、APX、Spatializer 3D、Q-SOUND、Virtaul Dolby、Ymersionなどが一般的です。実装方法は異なりますが、いずれも明確な立体音場効果を体感できます。中でも最初の3つはより一般的です。これらの技術はExtended Stereo理論を採用しており、回路を通して音響信号を追加処理することで、リスナーは音像方向が2つのスピーカーの外側にまで拡張されているように感じ、音像が拡張され、空間感覚と立体感が生まれ、より広いステレオ効果が得られます。さらに、アクティブ電気機械サーボ技術(主にヘルムホルツ共鳴原理を利用)、BBE高精細プラトー音響再生システム技術、そして「位相ファックス」技術という2つの音響強化技術があり、これらも音質向上に一定の効果を発揮します。マルチメディアスピーカーにおいて、SRSとBBE技術は実装が容易で効果も良好であり、スピーカーの性能を効果的に向上させることができます。

トーン
特定の、通常は安定した波長(ピッチ)を持つ信号、つまり口語的に言えば音の音色を指します。音色は主に波長に依存します。人間の耳は、波長が短い音に対しては高いピッチに反応し、波長が長い音に対しては低いピッチに反応します。波長によるピッチの変化は基本的に対数的です。異なる楽器は同じ音符を演奏しますが、音色は異なります。しかし、ピッチは同じです。つまり、音の基本波は同じです。
音色
音質の知覚は、ある音を他の音と区別する特徴的な性質でもあります。異なる楽器が同じ音色を奏でても、音色は大きく異なる場合があります。これは、基本波は同じですが、倍音成分が大きく異なるためです。したがって、音色は基本波だけでなく、基本波の不可欠な部分である倍音とも密接に関連しており、楽器や人によって音色が異なります。しかし、実際の説明はより主観的であり、むしろ神秘的に感じられるかもしれません。
動的
音の最も強い部分と最も弱い部分の比率で、dBで表されます。たとえば、あるバンドのダイナミックレンジは90dBです。これは、最も弱い部分のパワーが最も大きい部分よりも90dB低いことを意味します。ダイナミックレンジはパワーの比率であり、音の絶対的なレベルとは関係ありません。前述のように、自然界のさまざまな音のダイナミックレンジも非常に変化に富んでいます。一般的な音声信号は約20〜45dBですが、一部の交響曲のダイナミックレンジは30〜130dB以上に達することがあります。ただし、いくつかの制限により、サウンドシステムのダイナミックレンジがバンドのダイナミックレンジに達することはほとんどありません。録音装置の固有のノイズによって、録音できる最も弱い音が決まり、システムの最大信号容量(歪みレベル)によって最も強い音が制限されます。一般的に、音声信号のダイナミックレンジは100dBに設定されているため、オーディオ機器のダイナミックレンジは100dBに達することができ、これは非常に優れています。
全高調波
オーディオ信号源がパワーアンプを通過する際に、非線形成分によって入力信号よりも出力信号に生じる高調波成分のことです。高調波歪みは、システムが完全に線形ではないために発生し、新たに追加された全高調波成分の二乗平均平方根を元の信号の実効値(rms)で割った値として表されます。
投稿日時: 2022年4月7日