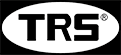私はこの業界に30年近く携わっています。「イマーシブサウンド」という概念が中国に持ち込まれたのは、おそらく2000年に機器が商用化された頃でしょう。商業的な利益の高まりにより、その開発はますます急務となっています。
では、「イマーシブサウンド」とは一体何でしょうか?
聴覚は人間にとって最も重要な知覚手段の一つであることは、誰もが知っています。ほとんどの人は、地面に倒れた瞬間から自然界の様々な音を集め始め、視覚、触覚、嗅覚といった知覚手段を長期間にわたって連携させることで、徐々に神経地図を形成していきます。時間をかけて、私たちは聞こえたものを地図化し、文脈、感情、さらには方向や空間などを判断できるようになります。ある意味では、日常生活において耳で聞き、感じるものは、人間にとって最もリアルで本能的な知覚と言えるでしょう。
電気音響システムは聴覚の技術的拡張であり、聴覚レベルで特定の情景を「再現」あるいは「再創造」するものです。私たちの電気音響技術への探求は、着実に歩みを進めてきました。技術の継続的な進歩により、いつの日か電気音響システムが、私たちが望む「現実の情景」を正確に再現できるようになることを願っています。電気音響システムの再現の中にいるとき、私たちはまるでその情景の中にいるかのような臨場感を得ることができます。没入感、「現実を忌む」、この代替感覚こそが、私たちが「没入型サウンド」と呼ぶものです。

もちろん、イマーシブサウンドについては、まだまだ探求を続けたいと思っています。人々にもっとリアルな感覚を与えるだけでなく、日常生活ではなかなか感じる機会や異例の体験ができないような光景を創り出せるかもしれません。例えば、様々な電子音楽が空中を旋回したり、クラシック交響曲を観客席ではなく指揮者の立場から体験したり…こうした日常では感じられない光景はすべて「イマーシブサウンド」を通して実現できます。これはサウンドアートにおける革新です。そのため、「イマーシブサウンド」の開発プロセスは段階的なものです。私の考えでは、XYZの三軸が揃った音情報だけが「イマーシブサウンド」と呼べるのです。
究極の目標であるイマーシブサウンドには、音場全体の電気音響的再現が含まれます。この目標を達成するには、少なくとも2つの要素が必要です。1つは、音源と音空間を電子的に再構築し、両者を有機的に融合させることです。そして、再生には主にHRTF(頭部伝達関数)ベースのバイノーラルサウンド、または様々なアルゴリズムに基づくスピーカー音場を採用します。

音の再現には、状況の再現が不可欠です。音の要素と音空間をタイムリーかつ正確に再現することで、生き生きとした「現実空間」を再現することができます。そのためには、様々なアルゴリズムと多様な表現手法が用いられます。現状、私たちの「没入型サウンド」が理想的とは言えないのは、アルゴリズムの精度と成熟度が不十分であることに加え、音の要素と音空間が著しく乖離し、緊密に統合されていないことが原因です。したがって、真に没入型の音響処理システムを構築するには、精度と成熟度の両方を考慮したアルゴリズムが必要であり、片方だけを追求するだけでは不十分です。
しかし、テクノロジーは常に芸術に奉仕するものであることを忘れてはなりません。音の美しさには、コンテンツの美しさとサウンドの美しさが含まれます。前者は、例えばライン、メロディー、調性、リズム、声のトーン、スピード、重厚感など、支配的な表現です。一方、後者は主に周波数、ダイナミクス、音量、空間のシェーピングなどを指し、サウンドアートの表現を補助する暗黙的な表現であり、互いに補完し合っています。私たちはこの両者の違いをしっかりと認識し、本末転倒になってはなりません。これはイマーシブサウンドの追求において非常に重要です。しかし同時に、テクノロジーの発展は芸術の発展を支えることができます。イマーシブサウンドは広大な知識分野であり、一言で要約したり定義したりすることはできません。しかし同時に、それは追求する価値のある科学でもあります。未知への探求、そして不断の探求は、電気音響学の長い歴史に確かな足跡を残すでしょう。
投稿日時: 2022年12月1日