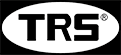音響技術の発展の歴史は、真空管、トランジスタ、集積回路、電界効果トランジスタの 4 つの段階に分けられます。
1906年、アメリカのデ・フォレストは真空トランジスタを発明し、人類の電気音響技術の先駆けとなりました。ベル研究所は1927年に負帰還技術の発明に成功しました。その後、オーディオ技術の発展は新たな時代を迎え、ウィリアムソン・アンプは負帰還技術を用いてアンプの歪みを大幅に低減することに成功しました。1950年代には真空管アンプの開発が最も刺激的な時期の一つを迎え、様々な真空管アンプが次々と登場しました。真空管アンプの音色は甘く丸みがあり、今でも愛好家に好まれています。
1960年代、トランジスタの登場により、多くのオーディオ愛好家がより広いオーディオの世界へと足を踏み入れるようになりました。トランジスタアンプは、繊細で感動的な音色、低歪み、広い周波数特性、そしてダイナミックレンジといった特徴を備えています。
1960年代初頭、米国はオーディオ技術の新たな一要素である集積回路を初めて導入しました。1970年代初頭、集積回路は高品質、低価格、小型、多機能などの理由から、音響業界で徐々に認知されるようになりました。現在までに、厚膜オーディオ集積回路とオペアンプ集積回路がオーディオ回路に広く利用されてきました。
1970年代半ば、日本は世界初の電界効果型出力管を開発しました。電界効果型出力管は、純電子管の特性、濃厚で甘い音色、そして90dBのダイナミックレンジ、THD < 0.01%(100KHZ)という優れた特性を有していたため、瞬く間にオーディオ機器の分野で普及しました。今日では多くのアンプにおいて、最終出力段に電界効果トランジスタが採用されています。
投稿日時: 2023年4月20日