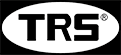音響システムの演奏効果は、音源設備とその後段の音響増強によって共同で決定されます。音響増強は、音源、チューニング、周辺機器、音響増強、接続機器で構成されます。
1. 音源システム
マイクは音響システムや録音システム全体の最初の接点であり、その品質はシステム全体の品質に直接影響を及ぼします。マイクは、信号伝送の形式によって有線と無線の2つのカテゴリに分けられます。
ワイヤレスマイクは、特に移動音源の収音に適しています。様々な場面での収音を容易にするために、各ワイヤレスマイクシステムにはハンドヘルドマイクとラベリアマイクを搭載できます。スタジオには同時に音響強化システムが設置されているため、ハウリングを防ぐため、ワイヤレスハンドヘルドマイクにはカーディオイド型単一指向性接話マイクを使用し、スピーチや歌声を収音する必要があります。また、ワイヤレスマイクシステムにはダイバーシティ受信技術を採用する必要があります。ダイバーシティ受信技術は、受信信号の安定性を向上させるだけでなく、受信信号の死角や死角を排除するのにも役立ちます。
有線マイクは、多機能、多場面、多グレードのマイク構成を備えています。言語や歌唱内容を収音する場合は、カーディオイドコンデンサーマイクが一般的に使用され、比較的固定された音源がある場所ではウェアラブルエレクトレットマイクも使用できます。マイク型超指向性コンデンサーマイクは、環境の影響を収音するために使用できます。打楽器には、一般的に低感度のムービングコイルマイクが使用されます。弦楽器、キーボードなどの楽器には高級コンデンサーマイクが使用されます。環境ノイズ要件が高い場合は、高指向性接話マイクを使用できます。大劇場の俳優の柔軟性を考慮すると、シングルポイントグースネックコンデンサーマイクを使用する必要があります。
現場の実際のニーズに応じて、マイクの数とタイプを選択できます。

2. チューニングシステム
チューニングシステムの主要部分はミキサーで、異なるレベルとインピーダンスの入力音源信号を増幅、減衰、動的に調整できます。付属のイコライザーを使用して信号の各周波数帯域を処理します。各チャンネル信号の混合比を調整した後、各チャンネルを割り当てて各受信端に送信し、ライブ音響強化信号と録音信号を制御します。
ミキサーを使用する際に注意すべき点がいくつかあります。まず、入力ポートの支持容量が大きく、周波数応答が可能な限り広い入力コンポーネントを選択してください。マイク入力またはライン入力を選択できます。各入力には、連続レベル制御ボタンと48Vファンタム電源スイッチがあります。このようにして、各チャンネルの入力部は、処理前に入力信号レベルを最適化できます。第二に、音響強化におけるフィードバックフィードバックとステージリターンモニタリングの問題のため、入力コンポーネント、補助出力、グループ出力のイコライゼーションが多ければ多いほど良く、制御が便利です。第三に、プログラムの安全性と信頼性を確保するために、ミキサーには2つの主電源とスタンバイ電源を装備し、自動的に切り替えることができます。音声信号の位相を調整および制御します)、入力ポートと出力ポートはXLRソケットであることが好ましいです。
3. 周辺機器
現場での音響強化では、スピーカーとパワーアンプを保護するために、音響フィードバックを発生させることなく十分な音圧レベルを確保する必要があります。同時に、音の明瞭性を維持し、音圧レベルの不足を補うために、ミキサーとパワーアンプの間に、イコライザー、フィードバックサプレッサー、コンプレッサー、エキサイター、周波数分割器、サウンドディストリビューターなどのオーディオ処理装置を設置する必要があります。
周波数イコライザーとフィードバックサプレッサーは、音のフィードバックを抑制し、音の欠陥を補い、音の明瞭性を確保するために使用されます。コンプレッサーは、入力信号の大きなピークに遭遇したときにパワーアンプが過負荷や歪みを引き起こさないようにするために使用され、パワーアンプとスピーカーを保護することができます。エキサイターは、音響効果を美しくするために使用されます。つまり、音色、浸透性、ステレオ感、明瞭度、低音効果を向上させます。周波数分周器は、異なる周波数帯域の信号を対応するパワーアンプに送信するために使用され、パワーアンプは音響信号を増幅してスピーカーに出力します。高度な芸術的効果プログラムを作成する場合は、音響強化システムの設計で3セグメント電子クロスオーバーを使用する方が適切です。
オーディオシステムの設置には多くの問題があります。周辺機器の接続位置と順序を不適切に考慮すると、機器の性能が不十分になり、機器が焼損することもあります。周辺機器の接続には一般的に順序が必要です。イコライザーはミキサーの後に配置します。フィードバックサプレッサーはイコライザーの前に配置しないでください。フィードバックサプレッサーをイコライザーの前に配置すると、音響フィードバックを完全に除去することが難しく、フィードバックサプレッサーの調整に役立ちません。コンプレッサーは、イコライザーとフィードバックサプレッサーの後に配置する必要があります。コンプレッサーの主な機能は、過剰な信号を抑制し、パワーアンプとスピーカーを保護することであるためです。励振器はパワーアンプの前に接続します。電子クロスオーバーは、必要に応じてパワーアンプの前に接続します。
録音したプログラムから最良の結果を得るには、コンプレッサーのパラメータを適切に調整する必要があります。コンプレッサーが圧縮状態になると、音質に破壊的な影響を与えるため、長時間圧縮状態を維持することは避けてください。コンプレッサーをメイン拡張チャンネルに接続する際の基本原則は、コンプレッサーの後ろにある周辺機器が信号ブースト機能を持たないようにすることです。そうでなければ、コンプレッサーは保護的な役割を全く果たせません。そのため、イコライザーはフィードバックサプレッサーの前に配置し、コンプレッサーはフィードバックサプレッサーの後に配置する必要があります。
エキサイターは、人間の心理音響現象を利用して、音の基本周波数に応じて高周波の倍音成分を生成します。同時に、低周波拡張機能により豊かな低周波成分を生成し、音質をさらに向上させることができます。そのため、エキサイターによって生成される音声信号は非常に広い周波数帯域を持ちます。コンプレッサーの周波数帯域が非常に広い場合は、エキサイターをコンプレッサーの前に接続することも可能です。
電子分周器は、必要に応じてパワーアンプの前段に接続され、環境やプログラム音源の周波数特性に起因する欠陥を補正します。最大の欠点は、接続とデバッグが面倒で、事故を起こしやすいことです。現在では、上記の機能を統合し、インテリジェントで操作が簡単で、優れた性能を備えたデジタルオーディオプロセッサが登場しています。
4. 音響強化システム
音響補強システムは、音響パワーと音場均一性の要件を満たす必要があることに注意する必要があります。ライブスピーカーを正しく吊り下げると、音響補強の明瞭度が向上し、音響パワーの損失と音響フィードバックが軽減されます。音響補強システムの総電力は、予備電力の 30% ~ 50 % を確保する必要があります。ワイヤレス モニタリング ヘッドフォンを使用します。
5. システム接続
機器の相互接続においては、インピーダンス整合とレベル整合を考慮する必要があります。平衡と不平衡は基準点を基準としています。信号の両端のグランドに対する抵抗値(インピーダンス値)は等しく、極性は逆であり、これが平衡入力または出力です。2つの平衡端子が受信する干渉信号は基本的に同じ値と極性を持つため、平衡伝送の負荷において干渉信号は互いに打ち消し合うことができます。そのため、平衡回路はコモンモード抑圧と耐干渉性に優れています。ほとんどのプロオーディオ機器は平衡接続を採用しています。
スピーカー接続では、線路抵抗を低減するために、短いスピーカーケーブルを複数本使用する必要があります。線路抵抗とパワーアンプの出力抵抗は、スピーカーシステムの低域Q値に影響を与えるため、低域の過渡特性が悪化し、伝送線路でオーディオ信号伝送中に歪みが発生します。伝送線路には分布容量と分布インダクタンスが存在するため、どちらも一定の周波数特性を持っています。信号は多くの周波数成分で構成されているため、多くの周波数成分で構成されるオーディオ信号群が伝送線路を通過すると、異なる周波数成分によって遅延と減衰が異なり、いわゆる振幅歪みと位相歪みが発生します。一般的に、歪みは常に存在します。伝送線路の理論的な条件によれば、R = G = 0の無損失条件では歪みは発生せず、絶対的な無損失も不可能です。有限損失の場合、歪みのない信号伝送の条件はL/R = C/Gであり、実際の均一伝送線路では常にL/Rです。
6. システムのデバッグ
調整前に、まずシステムレベルカーブを設定し、各レベルの信号レベルがデバイスのダイナミックレンジ内に収まるようにします。信号レベルが高すぎることによる非線形クリッピングや、信号レベルが低すぎて信号対雑音比が悪化することを防ぎます。システムレベルカーブを設定する際には、ミキサーのレベルカーブが非常に重要です。レベル設定後、システムの周波数特性をデバッグできます。
現代の高品質な業務用電気音響機器は、一般的に20Hz~20KHzの範囲で非常に平坦な周波数特性を持っています。しかし、特にスピーカーを多段接続すると、周波数特性が非常に平坦ではなくなる場合があります。より正確な調整方法は、ピンクノイズスペクトラムアナライザ法です。この方法の調整プロセスは、ピンクノイズを音響システムに入力し、スピーカーで再生し、テストマイクを使用してホール内の最適なリスニングポジションで音を拾うことです。テストマイクをスペクトラムアナライザに接続し、スペクトラムアナライザはホール音響システムの振幅周波数特性を表示し、スペクトル測定結果に基づいてイコライザを慎重に調整して、全体の振幅周波数特性が平坦になるようにします。調整後、オシロスコープで各レベルの波形を確認し、イコライザの大幅な調整によって特定のレベルでクリッピング歪みが発生していないかどうかを確認することをお勧めします。
システム干渉には、次の点に注意する必要があります。電源電圧は安定している必要があります。各デバイスのシェルはハムを防ぐために適切に接地されている必要があります。信号の入力と出力はバランスが取れている必要があります。配線の緩みや不規則な溶接が防止されます。
投稿日時: 2021年9月17日